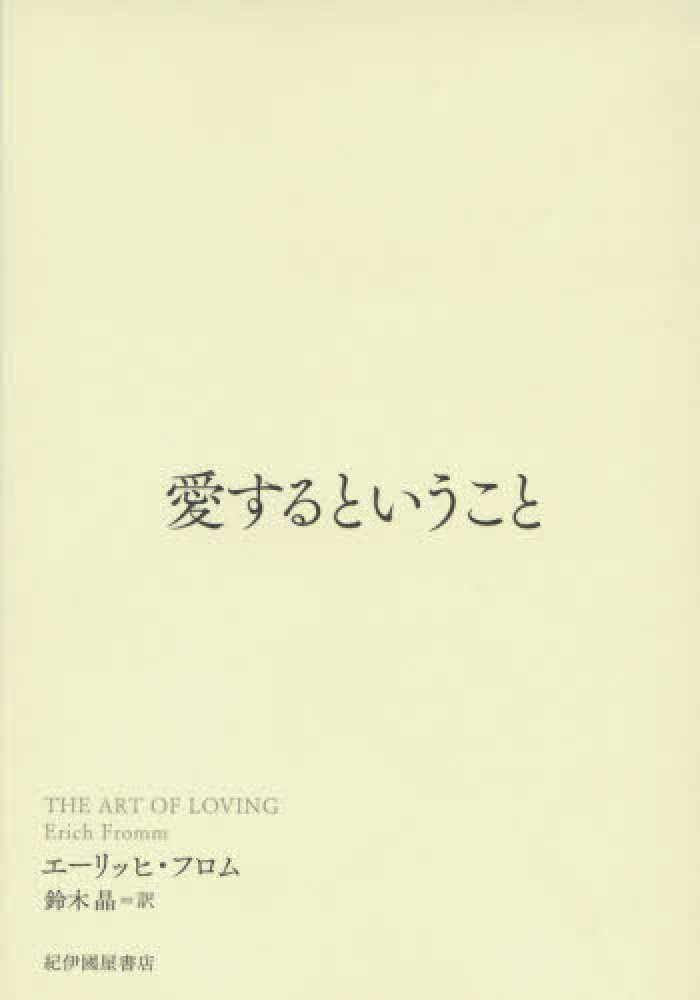「愛は技術である」という主張に惹かれ、エーリッヒ・フロムの『愛するということ』を読んでみました。
本書はかなり幅広い分野の知見に基づいていますが、原著の発表が1956年ということもあり、どの情報が現在も古びていないのかを見極めるのが難しいと感じました。例えば、現代の精神医学・心理学・文化人類学の観点からは、いくつかの点で批判が考えられるように思います。そのため、著者の主張を鵜呑みにすることはできませんでした。
しかし一方で、現代の資本主義社会の性質について、平易な表現で鋭く指摘されている点には考えさせられました。特に印象的だったのは、以下の一節です。
現代人にとって、幸福とは「楽しい」ということだ。楽しいということは、なんでも「手に入り」、消費できることだ。商品、映像、料理、酒、タバコ、人間、講演、本、映画などを、人びとはかたっぱしから呑みこみ、消費する。世界は、私たちの消費欲をみたすための、大きな物体だ。大きなリンゴ、大きな酒瓶、大きな乳房だ。私たちはその乳房にしゃぶりつき、かぎりない期待を抱き、希望を失わず、それでいて永遠に失望している。いまや私たちの性格は、交換と消費に適応している。物質的なものだけでなく精神的なものまでもが、交換と消費の対象となっている。
この指摘がなされてから70年近く経とうとしていることに衝撃を覚えます。「交換と消費」によって幸福を追求する傾向はむしろ加速しているように思いますが、ACTをはじめとする現代的な心理療法が挑み続けている課題でもあるのかなと感じました。